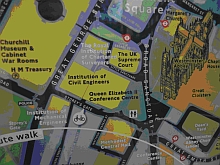日本機械学会会長の経験を通じて(その1)
東日本大震災対応

東京大学 大学院工学系研究科
機械工学専攻 教授 金子成彦
プロフィールはこちら
久しぶりにコラムに書かせていただきます。

6月は麦秋とも呼ばれます。我が家の家庭菜園もジャガイモの収穫時期を迎え、昨日収穫を終えました。今年の関東地方は陽気が安定しない年で、なかなか寒さが抜けきらないと思っていたら3月中に桜が咲き出し、4月の入学式の時期には散っていたという珍しい春を経験しました。雨も少なく、3月から6月初旬の間にまとった量の雨が降った記憶はありません。そのせいか、畑の中には例年に比べて虫が少なく、ミミズもあまりいません。土もパサパサしています。
さて、土のパサパサにはもう一つ理由があります。言い訳じみていますが、秋から年明けにかけて植えた大根を収穫した後の2月終わりから3月初旬に掛けての時期は、畑を寝かせて置かなければならない大事な時期です。しかし、今年は日本機械学会の会長職の引き継ぎ時期にあたり、畑の手入れに割ける時間が不足し、大根を引き上げた同じ週のうちに畑に肥料を施してジャガイモの種芋を撒いてしまいました。その結果、収穫されたジャガイモは小粒なものばかりでした。このように、手を抜くとすぐにバレテしまいます。
2012年4月から2013年4月までの1年間、創立以来116年の伝統のある日本機械学会の会長を務めさせて頂きました。日本機械学会では、2000年に会長選出方法が変更され、現在は、会員全員による投票により代表会員がまず選出され、その後、代表会員による第1回目の投票によって会長候補5名が選出され、さらに、第2回目の投票によって会長候補が決まる仕組みとなっています。このようにして選出された人物は次の年度の会長候補であり、選出された年度は、筆頭副会長と呼ばれ、会長補佐を務めることになっています。したがって、学会の運営には、実質的には2年間に亘って携わることになります。
小生が、筆頭副会長に選出された時期は2011年2月で、ひと月余り後の3月11日に東日本大震災が発生し、震災と併せて、引き続き発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故や電力不足問題に対する対応を学会として急がなければならない緊急事態を迎えました。学会執行部での相談の結果、日本機械学会ならではのデータに裏付けられた提言を目指して学会の総力を挙げた調査が開始されることになりました。日本機械学会には目下のところ21の部門と二つの専門会議と一つの推進会議があります。中でも、機械力学・計測制御部門に設置されている地震被害調査のための常設委員会は、阪神淡路大震災、中越地震などでも被害調査活動を行った実績があり、調査方法についてもノウハウが蓄積されていました。しかしながら、東日本大震災は、これまでのものと比較して調査対象も多岐にわたり調査範囲が比較にならないほど広かったために、関係する多くの部門や専門会議に協力をお願いしました。その結果、2012年6月には中間報告が纏められ、最終調査報告書が近々出版される運びとなっています。また、東日本大震災と引き続き発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故や電力不足問題では、学会と社会との関係や人材育成も問題となったため、これらについても長期的課題として検討対象に加え、以下のようなテーマのもと調査・提言分科会と長期的課題検討分科会を設置し、活動を開始しました。
・調査・提言分科会
WG1:機械設備の被害状況と耐震対策技術の有効性
WG2:力学体系に基づく津波被害のメカニズムの理解
WG3:被災地で活動できるロボットの課題の整理
WG4:被災地周辺の交通,物流分析
WG5:エネルギーインフラの諸問題
WG6:原子力規格基準の課題と今後の方向性
WG7:地震、原発事故等に対する危機管理
・長期的課題検討分科会
WG1:将来のエネルギー源・エネルギー利用に関する定量的評価と提言
WG2:人工物に対する信頼性・ロバスト性の確立と危機に対する管理制御方法
WG3:工学を社会に対して適正に説明する方法とそのための機械技術者の人材育成
WG4:福島原発事故の教訓から学ぶ工学の原点と社会的使命~安全・安心社会の
構築に向けて
少し歴史をひも解いてみることにしましょう。日本機械学会の初代会長は眞野文二先生です。1886年に英国に渡られた眞野文二先生はInstitution of Mechanical Engineers(略称:IMechE、英国機械学会)の会員となられ、同会の会員が大学の学位以上に尊ばれているという実情に驚き、帰国後、東京帝国大学機械工学科および東京高等工業学校機械科の卒業生を中心に1897年に設立されたのが現在の日本機械学会です。
小生は、2012年9月に学会と市民をつなぐ情報発信活動に関する調査を目的として英国機械学会を訪問する機会を得ました。英国機械学会は、英国土木学会と並んでバッキンガム宮殿からそれほど離れていないウエストミンスター地区に建物があり、存在感を示しています。しかし、事務局長さんの説明によって、その存在感は、市民への発信という形でより具体的に実現していることが分かりました。
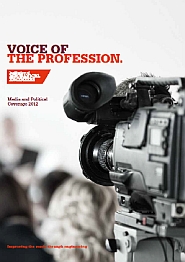 英国機械学会発行のデータ集
英国機械学会発行のデータ集
VOICE OF THE PROFESSION
英国機械学会は、毎年、ポリシーステートメントという冊子体を発行しています。内容は、様々で、その時に話題となっているテーマについてパブリックステートメントという形で4~5年前から市民や行政に向けての発信が開始されていました。驚いたことには、機械工学の重要性を市民に浸透した度合いを測るために、英国機械学会からの発信がどのようなメディアに取り上げられたかを定期的に調査しており、Voice of the Professionという名前のデータ集として纏められています。改めて、成熟社会での学会の役割を考えさせられた訪問でした。
東日本大震災は、工学者に多くのことを気付かせてくれました。その一つに、日本は戦後の急成長によって生活の豊かさや利便性を向上することには成功しましたが、人工物がもたらす負の側面やリスクに関しては専門家と市民との間にはコミュニケーションが十分にとれていたとは言えず、ある意味で発展を急ぎすぎた国だったということが挙げられます。また、エネルギー問題を始めとする日本の課題は過去の歴史を背負っており、簡単に解決できるものはありません。
解決の糸口を見出すために学会が果たせること、それは、工学者に自分の専門領域を越えた俯瞰的な見方を身に付けさせる機会を提供することだと思いました。これは、豊かな作物をもたらす肥沃な土壌の大切さを認識して用意することに似ています。
また、学会は専門分野に関しては目下の最新情報を持った人々の集う場所であり、最新のデータに基づいた議論ができるはずです。さらに、学会は年代を越えた技術者や研究者によって構成されており、過去のデータも扱うことができる集団です。したがって、今後の学会は、これまでのような仲間内に向けての発信だけでなく、市民に向けての発信機能を併せ持つ集団に変わって行くべきと考えます。ただし、市民向けの情報発信活動は、正確さと迅速さが求められるため、その役割は現役世代だけが担うものではなく、日本の人口のボリュームゾーンを形成している65-75歳までのアクティブシニアの参加を得て内容の充実を図るべきと考えます。
最後に、これからの工学者には、アイデアを形にする創造的活動だけでなく、社会実装の重みを感じさせる経験も積ませるべきで、それによって、様々な立場に立って考えるという発想を植え付けることができると考えます。一市民の側に立って考えることが習慣として身に付くように、学校教育の中でも科学技術リテラシーの時間を取って、リスクに対する説明や合意形成の方法を教えるべきと感じた次第です。
金子成彦
1976年 3月、東京大学工学部機械工学科卒業、1981年工学博士
1981年 4月、東京大学工学部講師
1982年 4月、東京大学工学部助教授
1985年 8月、カナダ・マギル大学客員助教授
2003年 1月、東京大学大学院工学系研究科教授
2012年 4月-2013年4月、日本機械学会会長(第90期)
専門分野: 振動音響学, 流体関連振動, 振動制御工学, 分散エネルギー工学

-
Vol.5 No.6
2013年06月11日号

-
WEBマガジンに掲載されている最新情報を毎月1回メールマガジンでお届けしています。
配信登録フォームよりお気軽にご登録ください。